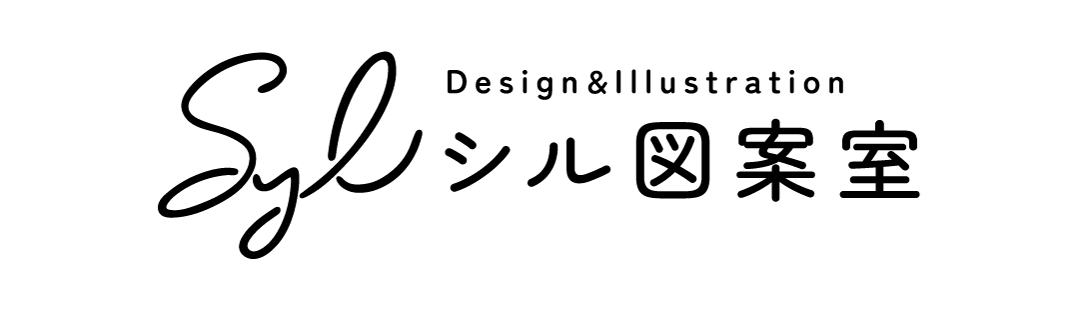幻の没作品「正解を出したがる男」小説所有権つき
正解を出したがる男.jpg
¥3,000 税込
SOLD OUT
購入後にDL出来ます (1119046バイト)
やむなく没になった小説と挿絵のセット。
小説はpdfデータで後日お送りします。
=====================================
※挿絵は画像のダウンロードにて納品となります。
※NFTを希望の方は、本サイトで決済の際、ウォレットアドレスを備考欄に記入するかDM等でお知らせください。後日NFTをトランスファーします。
※NFTのチェーンはpolygonとなります。
=====================================
小説全文を公開
正解を出したがる男
カラン、コロン。
「いらっしゃい。スナックくらげへようこそ。」
「えーと、初めてなんですけど、大丈夫ですかね?」
「あら、ウチはそういうの気にしないわ。どうぞ飲んで行ってちょうだい。て言っても、ハイボールかドクダミ茶しかないけどね。」
「じゃあ、ハイボールを。あ、濃いめでお願いします。」
今日は朝から選択に恵まれない日だった。
朝ごはんにパンを選んだらマーガリンがない。通勤に選んだ道が渋滞している。仕事で優先した案件が上手くいかない。おまけに、よく行くケーキ屋に新作が出ていたので奥さんに買って帰ったら、いつものが良かったと言われる始末だ。
流石の私も、「せっかく買ってきてあげたのにそれはないんじゃない?」と口走ってしまい、奥さんの機嫌は奈落の底へ真っ逆さまである。
そこから普段の溜まりに溜まった愚痴を百倍返しで吐き出され、とうとう居たたまれなくなった私は、しばらく家の外に出ることにしたのだ。
最初は散歩がてら、いつもは通らないような道を歩いていたのだが、ふと入った裏路地で、この「スナックくらげ」という水色の傘が掛かった入口が目に入り、何故だかふらっと中に吸い込まれてしまったという経緯である。
「ハイボールおまたせ。ちゃんと濃いめにしておいたわよ。」
「どうも。ここのママさん、ですよね?」
「人のことが知りたければ、まず自分の紹介が先なんじゃない?」
「あ、そうですよね。すみません…僕は」
「アハハ、冗談よ。ごめんね意地悪して。むしろお客さんの詮索はしない主義なの。」
「と言うわけで、この店のママ、シルです。」
ママは胸に手を当て、軽く頭を下げた。
「今日はどうしてウチに?わざわざ探して来てくれた…
とかじゃなさそうだし。」
私は今日の不遇な出来事とここへ来た経緯をママへ話した。
「それはツイてなかったわね。そしてあなた、普段からあまり奥さんと話したりしてないんじゃないかしら?」
「それは、まぁ。ある程度長いこと一緒に居ると、そんなに毎日話すことも無いですし。」
「そんなのその日あったこととか、何でもいいのよ。普段話したりしないから、そういう風にちょっとの不満が溜まっていって、些細なきっかけでダムが決壊しちゃうんじゃない?」
「でも話したら話したで理屈臭いとかいつも言われるので、そりゃ次第にこっちの口数も
減りますよ。」
「あ!もしかしてあなた、奥さんが悩み事とか話してくれてる時に、解決策を考えて提案しちゃうタイプでしょ。」
「え?当たり前ですよ。だって悩んでるんだから、それを解決しないことには悩みが無くならないじゃないですか。ちゃんと相手の納得感が得られる答えを出してあげないと。」
「なるほど、そういうところね。いい?女ってのは大抵、自分の話を聞いてほしいだけなの。もちろん全員がそうとは言わないけど、自分が思ってることを相手に話して、そうだねって共感してほしい。そういうものなのよ。」
「うーん、それじゃ相手に話す意味が無くないですか?その問題について自分がどうすれば良いか、その正解が欲しいから僕なら話しますよ。」
「はぁーっ。奥さんの気持ちが分かった気がするわ。」
「ため息を吐かないで下さいよママ…」
「…分かったわ。それじゃちょっとしたゲームをしない?」
「ゲーム?」
「あそこにドアがあるでしょう。そこに入りなさい。無事ここに帰って来れたら、その時は一杯奢るわ。」
「帰って来れたらって、帰って来れないかもしれないんですか?」
「フフッ。それはあなた次第よ。」
ママはウインクをしながらそう言うと、私を店の奥にある扉の前へと連れて行った。
「さぁ、いってらっしゃい。」
そう言われるがまま、僕はドアを開けた先の通路へと足を踏み入れた。
ドアが閉まる音を背中で聞きながら、薄暗い通路を進む。しばらく真っすぐ奥へと歩いて行くと、いつの間にか洞窟の様な、周りを岩肌で囲まれた、開けた場所に出た。
「なんだ、ここ…。」
天井も高く、とても広い空間だ。改めて周りを見渡すと、左手奥の方からこちら側に線路のレールのようなものが延びてきており、そのレールはカーブを描いて、向かって右側へと続いていた。
右側に延びたレールの先には4,5人の作業員がいるようだ。ヘルメットを被り、スコップか何かで掘るような仕草をしている。
その時。
左手奥から、もの凄い勢いで線路の上をトロッコが走ってきた!右手にいる作業員たちは全く気づいていない。このままだと作業員に追突してしまう。
何か術はないかと周囲を探すと、近くの壁にレバーがあった。
「分岐レバー」と書いてある。
「分岐…?」
今までは薄暗くて気づかなかったが、右側へ延びる線路の途中に分岐点があった。
そして分岐した線路の先にも、作業員が一人いた。
「レバーを倒せば、一人の方に切り替えられる…
いや待て!でもあの人は、本来関係なかったはずの人だ!」
トロッコがどんどん迫る中、私はそのレバーを下げることに決めた。どちらにしろ犠牲が出てしまうなら、少ない方を選ぼうとしたのだ。
そしてレバーを下げようとした正にその時、分岐先の作業員のヘルメットが落ちた。
その瞬間、私はアッと声をあげていた。ヘルメットの下から覗いた顔は、私の妻だったのだ。
「…え⁉なんでここに!」
そう言って僕はギリギリでレバーを下げることを踏み留まり、トロッコはそのまま線路を進んでいった…
刹那、強烈な光が私の眼に飛び込み、そこで意識は途切れた。
「戻ったみたいね。」
「えっ?…うっ……眩しい…」
気付くと私は、元いたスナックのカウンターにいた。
「どう?楽しかった?」
「どうって、何ですか今のは!妻が死ぬところだった!」
「フフフ、大丈夫よ。もちろん現実ではないわ。」
「あんなもの、選ぶことなんてできない。」
「そうね。でもあなたは答えを出した。奥さんでは無い方を犠牲にする、という答えをね。」
「当たり前ですよ。」
「でも奥さんじゃなければ1人を犠牲にしていた…
そういう事よ。」
「え?」
「後は自分で考えなさい。さ、そろそろ閉店よ。ハイボールは…奢ってあげる。」
私はその後しばらく店の外で立ち尽くし、頭の中で先程の出来事を反芻していた。
そして今日の帰りはいつものケーキを買って、奥さんに謝ろうと決めた。
[参考:trolley problem / Philippa Ruth Foot 1967]
-
お支払い方法について
¥3,000 税込
SOLD OUT